≪北アルプスの名峰≫
★☆☆槍ヶ岳登頂記☆☆★
○北アルプスを目指す
6月初めだったと記憶しているが、知人の居る山の会から槍ヶ岳登頂計画のお誘いを受けた。過去に槍ヶ岳には10年ほど前と50年ほど前の学生時代に登頂している が、今回のルートは過去に通過したことのない表銀座コースで、以前から一度はと望んでいたこともあり、参加することにした。
同行者は今年3月に退職したSF氏とOM氏、それに2年前に退職しマラソン友達のMS氏、 さらに自分を加えての4名である。
去る8月1日(土)午前9時半、「名鉄バスセンター」に全員集 合。参加を直前に取りやめたSM氏が差し入れにやってきて、見送ってくれた。乗車バスは定刻どおり10:00に出発。ほぼ満席である。すぐに名高速に入 り、小牧ICから名神高速に乗り、小牧JCか ら中央高速に入る。
天候はさほど良くないが、山々を眺めつつ、快適に走行。長い長い恵那山トンネルを抜けると長野県である。阿智SAで 休憩、右手には天竜川の彼方に雄大な南アルプスが見えるはずだが、今日は雲にかすんで眺望は利かず残念。
手前の山々を眺めて、あのあたりが塩見岳だとか、仙丈岳だとか想像して沿線風景を楽しむ。
左側には中央アルプスがあるが、こちらは山が迫って見上げてみるものの、ほとんど眺望は 利かず。やがて、諏訪湖辺りから長野自動車道へ入り、松本盆地を目指す。この辺りから睡魔に襲われ、あまり周辺の記憶がない。この高速道はマイカーで何度 も通過しているが、バスを利用したのは始めてで、この居眠りが出来るのは最大の効用である。松本城はどの辺りかなとうつらうつらしているうちに高速道を下 り、松本市内に入った。一般道は交通量が多い。ほどなく終点「松本バスターミナル」に着いた。駅ビル内にて遅めの昼食。
JR大糸線松本発14:09大 町行きに乗車、車中からの北アルプスの展望はよくない。乗り合わせた乗客と雑談しているうちに14:45穂高駅に着いた。
穂高駅にてタクシーを拾い、安曇野をドライブ。くねくねと屈折を繰り返し、次第に山の中 に入ってゆく。30年ほど前に家族旅行のとき、マイカーでこのルートを通ったはずであるが、そのと きの記憶はほとんどない。
15:30今宵の宿『中房温泉有明荘』に着いた。30年前にもここで宿泊したが、立て替えたのだろうか随分とイメージが異なっている。すぐに部屋に入って、旅 装を解き、雑談しながらしばらく休憩。外は小雨が降り続いている。夕食前にお風呂で今日の汗を流す。ここの温泉は安曇野では人気があり、登山基地ではある ものの、温泉を楽しむ客が多く宿泊しているようだ。

雨が滴り落ちる中での露天風呂もなかなか風情がある。明日からの山小屋泊では入浴は出来ないので、名 残惜しむが如くゆったりと浸かる。
お湯から上がって、すぐに夕食。食堂に入ると、各々のグループに食卓が用意されており、同行の諸氏た ちの酒豪ぶりにあきれながら、小一時間ほど至福のひと時を過ごした。夕食後は再度露天風呂に入ったり、TVな ど見て、9:30頃に就寝。
○合戦尾根から燕岳
翌8月2日(日)午前4時頃目覚めたまま、小川のせせらぎか 小雨の音か外の気配を感じながらまどろむ。窓外を眺めると予報どおり雨が降っている。
MS氏はすでに温泉に浸かってきたと言って張り切っている。早速に昨夜に用意されたおにぎりで朝食を済ます。大半の宿泊客はいまだ夢の 中、5時過ぎに出立の準備を済まし、玄関を出て記念撮影。午前5時半過ぎに小雨の中を出立。
登山口に向かうは我らだけである。途中日本猿の一群に遭遇、10匹ほどいたように思う。
30年前にも猿の一団に遭遇したのが、子供達に強い印象を残したようだ。
途中のマイカー駐車場は早朝からほぼ満車である。やがて、登山口に着いた。ここではマイカーで来た登 山者に出くわした。彼らはストレッチなど準備に余念がない。午前5時55分 いよいよ登山道に取りつく。いきなりの急登である。
身体はいまだに十分に目覚めておらず、はなはだしんどい。
この尾根は北アルプスで三大急登のひとつと言われているだけに、さもありなんと思う。ちなみに他の二つは烏帽子岳のブナ立ち尾根と笠が岳の笠新道で ある。
危険なところはないが、シラビソ(青森トドマツ)や白樺の茂る樹林帯の中をジグザグに登って高度をひ たすら稼ぐ。道中適当な間隔でベンチなどが配され、休息するに良いが、今日は小雨のうえ、登山者が多くて、思うように座れない。第三ベンチからはさらに急 登が続く。ここは合戦尾根といって中房温泉から燕岳を結ぶ人気ルートだけに登り下りの登山者がひっきりなしである。
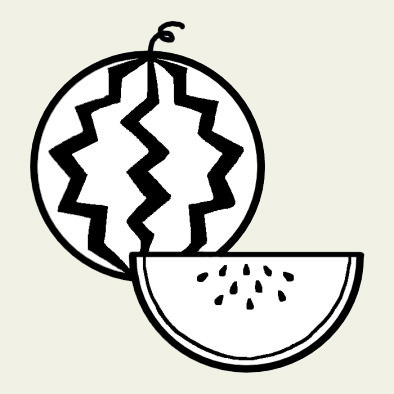
右手の谷を見下ろすと大きく崩れたところがあり、こんな所から土石流が発生し、下流に土砂災害を引き 起こすのだろう。
3時間ほどして尾根筋に近い「合戦小屋」に8:45に 着いた。登山客が多くたむろしている。ここの名物はスイカである。ほとんどの来訪者がかぶりついている。我々も早速に8分の1切れ800円を求め、これを 二人で分け合っていただいた。汗だくだくの後だけに美味が五臓六腑に染み渡る。この小屋は宿泊施設はなく、スイカをはじめ食事を供してくれるようだ。
傍らに合戦小屋の由来が掲げてあった。その由来によれば、桓武天皇の時代に有明山に八面大王と言う妖 術を使う鬼
 が住みついて、里に出ては財宝や婦女を略奪するなど乱暴狼藉を繰り返した。里人は甲子の年、甲子の
月、甲子の刻に生まれた矢村の矢助にこの鬼を討伐せんと要請した。そこで中房川上流の谷間で両軍の合戦が行われたことから、この小屋を合戦小屋と名づけた
ようだ。
が住みついて、里に出ては財宝や婦女を略奪するなど乱暴狼藉を繰り返した。里人は甲子の年、甲子の
月、甲子の刻に生まれた矢村の矢助にこの鬼を討伐せんと要請した。そこで中房川上流の谷間で両軍の合戦が行われたことから、この小屋を合戦小屋と名づけた
ようだ。八面大王は討ち果たされ、生き返らないようにその五体をばらばらにして、あちこちに埋葬 した。その一部が大王ワサビ園辺りも埋葬されたことから、ワサビ園にもこの合戦のことが記されている。
9:05小屋を辞し、燕山荘に向かう。天候が良ければ、ここからその山荘が望見 出来るそうだが、今日の天候では期待できない。ここからはなだらかな尾根筋を歩き、ミヤマキンポウゲなどの群落に癒されつつ、一時間ほどかかって10:05「燕山荘」に着いた。軒下にザックを置い て、身軽になって燕岳へ向かう。
ガスがかかったり切れたりして、指呼の間に眺められる燕岳はそれほど高度差は感じないの で、すぐにでも到達できそうである。燕岳は奇岩怪石の塊であるが、これが魅力にもなっている。メガネ岩を始めいろいろな形の岩石があり、まさに自然の造形 美である。それに高山植物の女王コマクサの群落がそこここに見かけられる。砂地の表面を覆うように咲いている姿はなんとも可憐で、ピンクの絨毯である。登 山路の周辺には咲いていない。砂が動くと種子が活着しないばかりか、不届きな登山者が摘み取ったり、ずけずけとカメラを構えて近づくからだろう。
30分弱で「燕岳山頂(標高2,763米)」に着いた。山荘から気軽に来られるの で、山頂周辺には来訪者が多い。天候が良ければ、雄大な槍ヶ岳やその北鎌尾根が眺められるはずだが、今日は近辺を眺めて我慢する。
さらに歩いて北燕岳に向かうグループがある。そちらにはもっと素晴らしいコマクサの群落があるよう だ。この辺り女性が多いのはコマクサに惹かれてやって来るからだろう。
帰り道はルート周辺の高山植物を楽しみながら、40分 ほど時間をかけて燕山荘に戻った。時刻は正午近くになり、山荘に上がり込んで、昼食を摂る。
天候さえ良ければ、窓から素晴らしい山々の景色が堪能できるのだが、今日は期待できず。食後、12:10に燕山荘を出立し、大天井ヒュッテに向か う。
○喜作新道
山荘の受付で大天井ヒュッテまでは4時間ほどかかると案内され、すぐに出発す る。小雨が降っているので、傘を差したまま前進する。もちろん沿線の眺めを楽しむことも出来ない。しばらく起伏も緩やかな尾根筋をのんびりと歩いて行く と、雷鳥に出会ったが、すぐに移動してしまい、充分に観察は出来なかった。ルートは尾根筋の右側に刻んであるが、所々左側には見上げる岩石が今にも崩れそ うで極めて不安定な様相を呈している。現に崩れ落ちた岩屑がいくらでも見られ、不安をそそる。そんなところは急いで通過する。
この喜作新道は大正の昔、猟師・小林喜作によって開拓された北アルプスの主峰槍ヶ岳への登山路であ る。従来の槍ヶ岳へのアプローチは燕岳〜大天井岳〜常念乗越〜槍沢〜槍ヶ岳であった。これを喜作は燕岳〜大天井岳〜西岳〜東鎌尾根〜槍ヶ岳へと開拓したの である。これによって大幅に時間短縮が可能になった。現在ではこのルートを表銀座といって多くの登山者で賑わっている。
これから考えるに喜作新道は大天井岳から槍ヶ岳の間を指すのだろうが、現在では燕山荘と大天井岳の間 も含めてのルートを称しているようだ。
二つほどのピークを越すところでは、登り下りを繰り返したが、難なく通過する。確か二つ目のピークを 巻き越す途中で、80歳を越す老齢の登山者が休んでおられ、二言三言言葉を交わした。娘さんとの二 人連れだそうだが、極めてゆっくりしたペースである。果たして明るいうちに山小屋へ行き着けるだろうかと他人事ながら心配になった。しかも小雨混じりの天 候の中である。
我々はペースを保って、前進する。そのうち切通岩に到達。まずは鎖と梯子を伝って大きく切れ落ち、次 に梯子で登り返す。そこの岩壁面に小林喜作のレリーフがあった。しかしゆっくりと眺める余裕もない。
この切通岩を過ぎて程なく、槍ヶ岳ルートと常念岳ルートの分岐点に着いた。
今宵の宿「大天井ヒュッテ」は槍ヶ岳ルート上にある。
ここからは大天井岳の北西山腹をトラバースして行く。これが中々の難所である。喜作の苦労が偲ばれ る。左手は大天井岳であるが、見上げるような高度があり、頂上は確認できないうえ、今にも崩れ落ちそうな岩稜が至る所に見られ、不気味なことこの上ない。 さらに右手は切れ落ちて奈落の底を覗かせている。そんなところには鎖が連続して岩壁面に取り付けてある。足元は昨夜来の雨で濡れており、滑りやすい。さら に滑落注意の看板もある。通常は落石注意が一般的である。この辺りでは過去に何人も滑落したのだろうか。
このような難所を何箇所も通過して、ガスの中、下方にヒュッテが俯瞰できたときは正直ほっとしたもの だ。
難行苦行の末、15:40大過なく『大天井ヒュッテ』に着いた。ロビーにてレインウエアーを脱いで一息。濡れた衣類をとりあえず乾 燥室に収納。部屋に落ち着いて一休み。今日は宿泊者が少なくて、10人部屋を我々4人で占領でき、ゆったり出来た。夕食は午後5時半。 今夜の宿泊者は30人程度である。食後は休憩室にて、明日の天気予報などを一喜一憂しながら見る。 天候によっては撤退するかどうかを議論しつつ、午後8時消灯となり、就寝。
○大天井ヒュッテから槍ヶ岳山荘へ
明けて8月3日(月) 午前4時前に窓外を仰ぐと星が空にちりばめた宝石のように見える。まさに快晴だ。昨夜山小屋の主人 と約束した「牛首展望台」へ向かうことにする。着替えて4時20分 ロビーにスタンバイ。
やがて、山小屋の主人が現れた。我々以外に数名が同行する。小屋から一気に高度を稼いで20分ほどで展望台に着いた。夜明けにはしばらく時間があるが、その展望に圧倒されてしまった。前方指呼の間 に北鎌尾根を従えた槍ヶ岳が天を突くかの如く屹立している。右の方へ目を転ずれば、薬師岳、水晶岳、立山連峰や剱岳が続き、さらに高瀬ダム湖のうえに針の 木岳がピラミダルな形を呈している。左に目を転ずれば大喰岳、中岳、南岳と3千米峰が南鎌尾根を形成して大キレットを隔てて、滝谷ドーム、北穂高、奥穂 高、前穂高と続く。

さらに遠方に乗鞍、御岳など。東方へ目を転ずると中央アルプス、奥に南アルプス連峰などを遠望、富士 山は手前の常念岳に隠れて見えない。
これらを山小屋の主人が指を差しながら逐一説明してくれる。我々は目を凝らしながら指先を懸命に追い かける。
こうして登山展望の醍醐味を十分に味わった。次第に近くの山々が赤く染まってくる。いよいよ日の出 だ。シャッターチャンスを逃さないように山々を背景に記念撮影。ここでの日の出は大天井岳の陰になるだけにまだまだ時間がかかりそうである。いまだ完全に 明け切っていないが、次の予定もあり、後ろ髪引かれる思いで展望台を後にした。
山荘には5:30前に帰り、朝食の食卓に着いたのは我々展望台帰りのグループだけとなった。他の宿泊者はすでに出立してい た。
6:05山荘を出発。いよいよ喜作新道の真髄をトレースして行く。しばらくは尾 根の東側で、ダケカンバやナナカマドの中を朝日を浴びながら、時おり、東方はるかに望む高峰に見守られて距離を稼ぐ。そのうちにぽこっと尾根筋に出たとこ ろが、ビックリ平である。正面に槍ヶ岳の勇姿が迫り、名前の通りまさにビックリする。我々は牛首展望台でこの状景は充分に堪能してきただけにそれほど驚か なかったが、始めてこの展望に接するものにはまさにビックリであろう。また感動の一瞬でもある。休憩用ベンチもある。
我々は荷物の不具合を修正して、すぐに出立。これからは尾根筋歩きなので誠に快適な山行となる。
この辺りからしばらくは尾根筋にルートが拓かれており、天候にも恵まれて、両側とも雄大な北アルプス の眺望を楽しみながらの至福の山歩きとなる。
時おり休憩して水分補給しながら、写真を撮ったりする。富士山もうっすらと姿を現してきた。正面に 槍ヶ岳を見上げつつ、次第に近づくこのコースを表銀座と名づけたのはぴったりのネーミングかなと実感する。
やがて赤岩岳を過ぎると尾根筋を離れ、続く西岳の東側を巻いて進むと「ヒュッテ西岳」が 見えてきた。ヒュッテ到着は8:46。ベン チが槍ヶ岳に向かって揃えてある。東鎌尾根から頂上に向かって穂先が屹立する槍ヶ岳の姿は荘厳なまでの感じさえする。ベンチで水分補給しながら見上げてい るとこれから登頂する意欲がふつふつと湧いてくる。
9:10ヒュッテを出立。すぐに大下りにかかる。西岳南面を巻いて下るが、最近 の岩雪崩の崩壊面が見上げられ、今にも落石しそうな様相のうえ、行く手には崩壊した巨大な岩屑が散らばっている。
先を行くグループも声を掛け合って慎重に進んで行く。まさに生きた心地がしないような数分だった。
大下りを過ぎて、馬の背を登り下りを繰り返して、水俣乗越にかかる。脇見しながらの歩行は危険であ る。この辺りには鎖場あり、垂直に近い梯子もあって、喜作新道のうちで最大の難所かと思う。
梯子を降りるときには足が震えてしまう。これは加齢のせいだろうかと痛切に感じた。下方を見やるとい やがおうにも地獄の底が目に入ってしまうため、どうしても恐怖感に襲われる。
水俣乗越を過ぎるといよいよ東鎌尾根の難儀な登りの連続となる。喜作の苦労を垣間見るようなものだ。 これらの内容は「ああ野麦峠」で名高い作家・山本茂美の書いた「喜作新道」に詳しい。
ここから槍ヶ岳の肩までの難所のルートはとても表銀座コースなどというロマンチックな表現から程遠 い。自分はかって10年ほど前に西鎌尾根を辿る裏銀座コースから槍ヶ岳にアプローチしたことがある が、そちらの方がはるかにやさしいルートであり、わき見しながらの山行が楽しめる。
水俣乗越を過ぎてやれやれとしたところで、昼食をする。天候が良くて、暑いほどだが、雑談しながらの 昼食時間は何物にも変えがたいひと時である。また、アルプスの雄大な景色を眺めつつのしばしの一時は登山の醍醐味でもある。
続く東鎌尾根のやせ尾根を次々とクリアーして「ヒュッテ大槍」に着いたのは12:40だった。まじかに迫った槍ヶ岳は天を突きあ げる如く屹立している。
これを眺め上げながらベンチで喉を潤した。ここを13:00に出立した。左手の下方に殺生ヒュッテがある。ここは従来「殺生小屋」と言って喜作が建立したもので、喜 作はここを拠点に、狩猟活動を続けていた。このことも前述の「喜作新道」に詳しく記されている。約一時間の難行を頑張り、14:00無事に『槍ヶ岳山荘』に着いた。
○にぎやかな槍ヶ岳界隈と槍ヶ岳登頂
この山荘は標高3千米にあり、収容能力1,000名を越すマンモス山小屋で、 アルピニストにも人気ナンバーワンである。山荘前の広場には登山者が所狭しとたむろし、それぞれ記念撮影、食事などにぎやかに談笑している。
すぐに受付に行く。ここでも行列である。我々愛知県人は4年 前に開催された愛・地球博で行列には慣れているはずだが、いらいらしてくる。
指定された部屋に落ち着いて一休み。今日は例年に比べ、天候不順のためか6〜7割の混み具合のよう だ。
身軽になって、いよいよ「槍ヶ岳山頂(標高3,180米)」 を目指す。
山荘前広場にてスタンバイし、穂先を見上げると登頂者が途切れることなく、岩稜に張り付いているのが よく分る。いよいよ穂先に取り付く。最初は緩やかな勾配であるが、すぐに急な登りになり、鎖場が続き、梯子もある。それに登りと下りのルートが分れ、この 高峰の人気のほどを痛感する。前後を登頂者に挟まれ、スタートしたらいやがおうにも進まねばならない。留まれば渋滞が発生する。鎖は二人が同時に掴まるの はご法度であり、梯子もしかり。
したがって、どうしても時間がかかる。悪戦苦闘を繰り返し、標高差180米を30分強かけて、午後3時20分頃頂上に到達。頂上の広場には20人ほどが立てる広さがあり、祠や三角点がある。祠の前で順番を待って記念撮影。
残念ながら頂上滞在中はガスがあり、遠望は期待できなかった。しばらく滞在し、ガスの晴れ間を期待し たが、結局あきらめて退散。
頂上からの下りはさらに緊張を強いられた。直下にはほぼ垂直に近い梯子が2本あって、いずれも20数段の長さがあり、どうして も足をかける位置を確認するたびに遥か下方が目に入り、足が震えてしまい、ピッチが上がらない。梯子が終わると今度は鎖場が連続し、鎖は固定されてないの で、揺れてしまう。そのたびに脂汗をかきつつ、慎重に下る。
槍ヶ岳は今回3度目の登頂である。最初は学生 時代で50年前、前回は約10年前であっ た。過去にはこのような恐怖感を感じなかった。やはり加齢には勝てない。これが最後の登頂になると感じながらの下山となった。

午後4時20分頃山荘前に下山した。先行していた同行者二人は生ビール片手に乾杯の準備をしていた。早速傍らのテーブ ルに陣取り、祝杯を挙げる。
周りのテーブルでも他のグループがそれぞれ談話を楽しんでいる。
したたかに酔ってしまい、部屋に戻って夕食前のひと時を休息しながら槍ヶ岳登頂の満足感を味わう。
窓からであるが、双六岳方面に沈み行く日の入りをしばし眺める。
夕食は交代制で、我々は午後6時のグループで ある。食堂は一度に150人ほどが同時に出来る広さがある。巨大レストランといった感じである。
夕食後は消灯までに時間もあり、絵葉書を4枚ほど書き上げたが、山荘では郵便を扱ってくれない。かっ ては山小屋からの便りには人気があったものだが、現今では郵政民営化のために廃止されてしまい、登山者の楽しみが一つ減ったような感じだ。結局上高地まで 下りてから投函した。
大部屋へ戻り、それぞれ雑談して過ごす。ロビーには天気予報のTVが放映されて、明日の天候を期待し て眺める。明日も快晴のようだ。
午後8時半に消灯となり、就寝。
○ご来迎を拝んで槍沢を下る
明けて8月4日(火) 周りがざわついて来て、午前4時頃目覚める。快晴らしい。ここから眺めるご来迎は素晴らしい。昨夜 の案内板に寄れば日の出は4:56である。4時半ごろに起き出し着込んで、ご来迎を拝みに出かける。もう既にほとんどの宿泊者は起き出している。

ロビーは靴を履く登山者でごった返している。山荘前広場に出て、槍ヶ岳の穂先を見上げるとランプの光 がちらちらしている。頂上でご来迎を拝もうとしている登山者の行列である。一人くらい落ちてこないかなと不謹慎な気持ちでしばし眺め上げる。ここではご来 迎は槍ヶ岳山体の陰になって見えないので、テント場の方へ移動する。大勢の登山者が寒さ対策にしっかり着込んで今か今かと固唾を呑んで、ほのかに明るく なった東方へいっせいに向いている。カメラを構えている者も多い。
やがて空が赤みを増してきて、槍ヶ岳の右肩の方からご来迎が差してきた。
いっせいに歓声が上がる。皆の顔もご来迎でほんのりと赤みが差してきた。2枚ほどシャッターを切る。
振り返って西の方を見ると、ピラミッド型の笠が岳に朝日が差して美しい姿を呈している。しばらくうっ とりしながらご来迎がもたらす山々の姿を今生の思い出とばかりしっかりと脳裏に刻んだ。
朝食は午前5時半頃ににぎやかな 食卓を囲んで済ました。
6:05に槍ヶ岳山荘を出立。いよいよ槍沢を下って、帰路についた。これからは ほぼ17キロをひたすら歩いて、上高地に向かうのである。
前後には山荘を後にする登山者が次々と下って行く。しばらく急坂を下って、雪渓を二箇所ほど過ぎる と、「播隆窟」という石窟があった。ここは槍ヶ岳を開山した念仏行者・播隆上人が念仏三昧で過ごした石室である。

上人は江戸時代後期の文政・天保年間(1830頃) に笠が岳に登頂して、遥かに見える槍ヶ岳の神々しい姿に魅せられ、難行苦行の末、槍ヶ岳に5度に 渡って登頂したそうだ。ルート開拓や鎖場の打ち込みも上人の業績である。
中を覗いてみると奥に思いのほか広いスペースがある。ここで上人は53日間に渡って念仏に明け暮れたそうだ。
上人の不屈の精神に頭の下がる思いを残して、さらに下って行く。以後三箇所ほど雪渓をやり過ごした が、この時期の雪渓はさほど危険ではない。勾配もそれほど急でもなく、先行者達の足跡を辿って行けば安全である。
やがて潅木の生い茂るあたりになると心なしか勾配も緩やかになってきた。
天狗原の分岐点で10分ほど休憩。天狗原には 太古の昔氷河で出来た湖沼があり、ここに写る逆さ槍ヶ岳は中々の風情があるそうだ。
さらにどんどん下って行く。下から登ってくる登山者にも次々すれ違い、槍沢も活気を帯びてくる。大曲 あたりに水俣乗越分岐点あり、ここで5分ほど一休み。昨日にはここから上りきった峠辺りで悪戦苦闘していたことを思い出す。
樹林が密度を増し、日陰が心地よい。右側からは槍沢の涼風に癒されて進むうち、大崩壊跡に遭遇。今年 の5月17日(日)の昼間に左岸上空の赤沢 山の山肌が大崩壊を起こし、巨大な岩雪崩となって、登山道を埋め尽くしたそうだ。
付近一帯は崩壊した巨大な岩屑で覆われている。岩肌を見上げると今にも続いて崩壊しそうな様相を呈し ており、誠に不気味である。不安に駆られて急いで通り過ぎる。この間ほぼ10分がとてつもなく長く 感じられた。
すぐに到達したババ平には赤沢岩小屋があり、多くの登山者が休憩していた。
そこに冷たい水道が引いてあり、しばし渇きを癒した。続いて9:25「槍沢ロッジ」に着いて、売店にて飲み物を購入し、しっかりと休憩。ベンチもあり其処ここに登山者が休憩している。先ほどの大崩壊のことにつ いて尋ねると、当時を体験した係員が応対してくれたが、地震かと思われるほどの巨大な地響きがしたそうだが、幸いなことに一人も巻き込まれなかったそう だ。
ロッジを9:45に出立。このあたりから歩行順序が定着してきた。先行はSF氏 とMS氏、続いて自分、しんがりはリーダーのOM氏 である。
OM氏は沿道風景を撮影しながら、我々をじっくり見守りつつ、ゆっくりと着実に追従してくれる。
10:18一の俣沢出合に着いた。ここは常念乗越からのルートがあり、水量豊富な 沢でもある。槍沢の水量が一気に増加した。もういっぱしの河川の様相を呈している。槍沢の水流を右に眺めつつ、樹林帯の中を快調に歩き、11:10に「横尾」に着いた。先行の二人はピッチが 早い。横尾に着いたときはビールで喉を潤し、一息入れていた。全員揃ったところで横尾山荘内で早めの昼食。
ここは穂高岳山麓の涸沢への分岐点である。その涸沢から流れ出る横尾谷を合流すると槍沢は梓川とな る。
この梓川は北安曇野市内で、槍ヶ岳北面を源流とする高瀬川と合流し、犀川となる。さらに下って、川中 島の古戦場あたりで千曲川と合流し、信濃川という我が国最長の大河川となって北信濃を貫流し、新潟県で日本海に注ぐ。
さて、横尾を11:45に出立。緩やかになった梓川沿いのルートを下って行く。車が通れるほどの広さになった登山道はゆったりと して歩き易い。
ほぼ一時間の歩行で、「徳沢園」に着いた。ここまで来るとハイカーや家族連れが多くなっ てきた。いわゆる山靴を履いてない来訪者が目立つ。
20分ほど休憩して、13:00に 出立。右手に流れる梓川は水量が多くなり、涼風をもたらし、コナラ、ブナなどの樹林帯も密度が濃くなり、美味しい空気を与えてくれる。まことに快適なハイ キングとなった。時間さえ許せばもっとゆったりと歩きたいような雰囲気である。
45分ほどで「明神」に着いた。人出が多くなり、完全にハイカー達の天国となってきた。上高地まで一時間ほどの距離だけに夏休みを利用し てやってきた家族連れが多い。ベンチもあり、三々五々腰掛けてにぎやかに談笑している。
我々も14:00に出発、いよいよ最終の歩行である。ここまでくれば時間的に余裕も出来、ゆったりと樹林豊かなルートを満 喫しながらの歩行である。前後に歩行者が多くなってきたのには、うんざりしないでもない。やがて小梨平のキャンプ場が見られると、「上高地」である。河童 橋あたりになると人・人・人で溢れている。下界に入ってきたことを実感。それにスピーカーからアナウンス音がひっきりなしに聞こえ、喧騒を極めている。
乗車バスを予約してから、近くのシャワー室に駆け込んで、三日間の汗を流した。16:00発の乗車バスは満席で積み残しも出るほど で、さすがに上高地は人気の避暑地。バスも次々とスタンバイしている。新島々へ17:05に着いて、松本電鉄に乗り換えた。こちらはゆったりと座席を確保でき、睡魔が襲ってきたが、30分ほどで、「松本」に着いた。早速に駅ビルの食堂階に上がり、そばを注文して、生ビールで無事帰還を乾杯 する。その後お土産を少々購入して、バスターミナルへ向かう。
○あとがき
19:10に定刻通りにスタートした乗車バスは、我々4名以外に乗客は3名という超ガラガラの最終便であ る。
おつまみなど食べながら暮れなずむ松本盆地に別れを告げていると、すぐに暗闇がやってき た。快いバスの振動に身をゆだねて、うたた寝を楽しむ。
22:24定刻どおりに「名古屋バスセンター」に到着。ここで諸氏に別れを告げ、 家路についた。
今回の山行は、4年前の御嶽山登頂以来であ り、槍ヶ岳は10年ほど前の登頂以来の再訪である。それも表銀座コースという魅力に誘われての参加 だった。
ところが、この表銀座コースが中々の曲者で本文中でも詳述したように、鎖場や梯子が至る所にあり、そ の通過には冷汗の連続であった。槍ヶ岳の穂先の登頂はさらに難行苦行で、足の震えが止まらなかった。これらを考えるに猟師・小林喜作の苦労が偲ばれ、また 播隆上人の偉業を賞賛せざるを得ない。
前回に登頂したときには、さほど恐怖感を感じなかったが、今回の恐怖感覚は加齢に伴う精神力やバラン ス感覚などの低下に基づくものと思える。したがって、槍ヶ岳登頂を目指す者には若いうちに挑戦せよとアドバイスしたい。
奥穂高岳や剱岳などの岩稜の高峰もしかりである。
槍ヶ岳を登頂している者を観察するとメタボな者は見かけない。山へ出かけるからメタボにならないの か、メタボな者は山へ出かけないのか、判断に苦しむが、いずれにしても山歩きは健康増進の良薬になっているようだ。
今回は数々の良き冥土の土産が出来たと思う。同行の諸氏に改めてお礼申し上げたい。もう二度とかかる 高峰に挑むことはないであろう。

平成 21年 9月上旬 回 想
名東区の修行ランナー KK
“健康は人生最高の財産”
“槍ヶ岳は若いうちに登頂 せよ”